広告
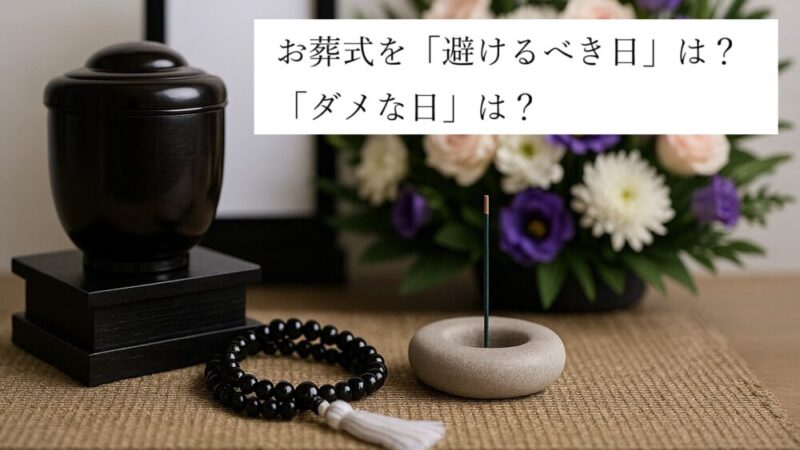
お葬式の日程を決める際、日柄やカレンダーの見方に悩む方は少なくありません。特に、死後何日後にお葬式を行うべきか、何時から始めるのが適切か、平日や日曜日の開催は問題ないのかなど、さまざまな疑問が浮かぶものです。事故死の場合のお葬式は何日後が良いのか、翌日や1週間後に行うケースはどうなのかといった点も気になるところでしょう。
また、お葬式を「避けるべき日」や「ダメな日」としてよく知られる友引や仏滅、大安などの六曜に関する考え方も、地域や宗教によって異なります。お通夜を行うべきでない日柄があるのか、そもそも六曜を気にする必要があるのかなど、判断に迷う場面も多いはずです。
この記事では、お葬式を「避けるべき日」「ダメな日」というテーマに沿って、お葬式の日程の決め方や注意点をわかりやすく解説します。失敗や後悔を避けるためにも、正しい知識を身につけておきましょう。
- 本記事で説明するポイント
- ・お葬式の日程と日柄の関係性
・友引や仏滅などお葬式を避けるべき日の考え方
・火葬場や僧侶の都合による葬儀日程調整の方法
・地域や宗教による違いと配慮のポイント
お葬式を「避けるべき日」「ダメな日」についての考え方

ここではまず、お葬式の日程や日柄を気にする理由、お葬式は死後何日後・何時からが一般的か、お葬式を翌日や1週間後に行うケース、お葬式の平日・日曜日など曜日による開催事情、事故死の場合のお葬式は何日後に行うべきかなどについて解説し、お葬式を「避けるべき日」「ダメな日」についての考え方について紹介します。
お葬式の日程や日柄を気にする理由とは
日本においてお葬式の日程を決める際に「日柄」を気にする風習は、古くから根付いています。その背景には、六曜(ろくよう)と呼ばれる暦注の存在があります。六曜とは、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6つの分類で、各日の吉凶や時間帯の運勢を示すものです。もともとは中国から伝わった占いの一種で、鎌倉時代末期から室町時代にかけて日本に広まり、江戸時代には庶民の間でも広く使われるようになりました。
冠婚葬祭の予定を立てる際には、六曜が記載されたカレンダーを参考にすることが一般的です。特に「友引」は、漢字の印象から「友を引く」と解釈され、故人が友人を道連れにするという迷信があるため、お葬式の日取りとして避けられる傾向があります。実際、友引の日には火葬場が休業となる地域も多く、お葬式を行ううえで実務的にも影響があります。
また、「仏滅」は「仏も滅するほどの凶日」とされ、縁起が悪いと考えられがちです。「赤口」も午前11時から午後1時以外は凶とされ、火や血を連想させることから避ける人もいます。これらの日柄は宗教的な根拠があるわけではなく、あくまで民間の風習や迷信に基づくものです。
とはいえ、参列者の中には日柄を気にする方も少なくありません。遺族としては、そうした感情に配慮することが求められます。日柄を気にするかどうかは、家族でよく話し合い、地域の慣習や参列者の意向を踏まえたうえで、納得のいく日程を選ぶことが大切です。
お葬式は死後何日後?何時からが一般的?
日本では、お葬式の実施に関して法律上の制約があります。具体的には、死体埋葬火葬法により、死亡後24時間以内の火葬は原則として禁止されています。これは、誤診による生き返りの可能性を排除するための措置であり、例外的な事情がない限り厳守されます。
そのため、亡くなった当日にお葬式を行うことはできず、一般的には以下の表のような流れになります。
| 臨終当日: | 遺体を自宅または安置施設へ搬送 |
| 翌日: | 通夜(仮通夜・本通夜)を実施 |
| 翌々日: | 葬儀・告別式および火葬 |
この流れに従えば、お葬式は死後2〜3日目に行われることが多く、開始時間は午前10時〜午後1時頃が一般的です。これは火葬場の稼働時間や僧侶の読経時間、参列者の移動時間などを考慮した結果です。
ただし、地域によっては通夜を亡くなった当日に行う場合もあり、また「骨葬」と呼ばれる火葬を先に済ませてから葬儀を行う形式も存在します。さらに、近年では通夜を省略する「直葬」や、通夜とお葬式を1日で済ませる「一日葬」など、形式の多様化が進んでいます。
これらの形式を選ぶことで、日程の柔軟性が高まり、遺族や参列者の負担を軽減することが可能です。状況に応じて、最適な日程と形式を選ぶことが求められます。
お葬式を翌日や1週間後に行うケースはあるか?
上でも説明したとおり、お葬式は死後2〜3日目に行われることが一般的ですが、必ずしもこのスケジュールに従う必要はありません。例えば、上でも紹介しましたが、通夜と葬儀を1日で済ませる「一日葬」など、お葬式を翌日に行うこともあります。
また、さまざまな事情により、お葬式が1週間後などにずれ込むケースもあります。お葬式が1週間後などにずれ込む代表的な要因としては以下の通りです。
- 火葬場の予約が取れない
- 僧侶の都合がつかない
- 年末年始や大型連休で葬儀社が休業
- 友引の日を避けるために調整が必要
特に都市部では火葬場の混雑が激しく、希望する日時に予約が取れないことも珍しくありません。また、友引の日を避けるために、遺体を数日間安置する必要がある場合もあります。
このような場合には、遺体の衛生管理が重要になりますが、保冷措置を施すことで、遺体を1週間程度衛生的に保管することが可能です。ドライアイスや冷却装置を用いた安置方法が一般的で、葬儀社が適切に対応してくれます。
家族や関係者と相談しながら、無理のないスケジュールを組むことが大切です。精神的な整理や参列者の調整も含め、柔軟な対応が求められます。
お葬式は平日?日曜日?曜日による開催事情
一般的にお葬式は平日に行われることが多いですが、日曜日に開催されるケースもあります。それぞれにメリットと注意点があり、日程を決める際には慎重な判断が必要です。
【平日の葬儀の特徴】
- 火葬場や葬儀場の予約が取りやすい
- 僧侶のスケジュールが合わせやすい
- 施設利用料が通常料金で済む
【日曜日の葬儀の特徴】
- 参列者の都合がつきやすい
- 遠方からの移動がしやすい
- 施設が混雑しやすく、追加料金が発生する場合もある
特に注意すべきなのは、友引の日が日曜日に重なる場合です。この場合、火葬場が休業している地域も多く、お葬式の実施が困難になる可能性があります。事前に火葬場や葬儀場の営業日を確認し、予約状況を把握しておくことが重要です。
また、日曜日は複数のお葬式が重なることもあり、式場の利用時間が制限される場合があります。参列者の利便性だけでなく、施設の運営状況も考慮したうえで、最適な日程を選ぶことが望ましいです。
事故死の場合のお葬式は何日後に行うべきか
事故死の場合、通常の自然死とは異なり、警察や医療機関による検死や法的手続きが必要となります。これにより、お葬式の日程が延びることが一般的です。
検死とは、死因を明確にするために行われる医学的・法的な調査であり、交通事故や転落事故、突然死などの場合に実施されます。検死が完了するまで遺体の火葬は認められず、死亡診断書や死体検案書の発行を待つ必要があります。
このため、事故死のお葬式は死後3日〜7日後に行われるケースが多く、状況によってはさらに延びることもあります。遺族は精神的なショックを受けていることが多いため、無理のないスケジュール調整が求められます。
また、事故死の場合は報道対応や保険会社との連絡、関係者への通知など、通常のお葬式以上に準備すべき事項が多くあります。火葬場や僧侶の都合、参列者の予定なども踏まえ、慎重にスケジュールを組むことが重要です。
事故死に限らず、急な死去では精神的な整理も含めて、柔軟な対応が必要です。葬儀社や医療機関との連携を密にしながら、適切なタイミングでお葬式を執り行うようにしましょう。
お葬式を「避けるべき日」「ダメな日」をどう判断する?

続いて、お葬式を「避けるべき日」としての友引の意味、お葬式が「ダメな日」大安や仏滅は避けるべきか、お葬式が「ダメな日」の「日取りカレンダー」、お通夜が「ダメな日」とされる日柄などについても詳細に解説し、お葬式を「避けるべき日」「ダメな日」をどう判断するかについて理解を深めます。
お葬式を「避けるべき日」としての友引の意味
日本の暦における六曜のひとつである「友引」は、冠婚葬祭の予定を立てる際に特に意識される日柄です。友引は本来「勝負がつかず引き分ける日」という意味を持ちますが、現在では「友を引く」と解釈されることが一般的になっています。この解釈から、お葬式の日取りとしては不吉とされ、避けられる傾向があります。
特に年配の方や地域の風習を重視する方々の間では、友引の日にお葬式を行うことは「故人が友人を道連れにする」といった迷信的な考え方に基づき、忌避されることがあります。こうした考え方は宗教的な教義に基づくものではなく、民間の風習や文化的背景によるものです。
実務面でも、友引の日には火葬場が休業となる地域が多く、お葬式のスケジュール調整が困難になる場合があります。これは、利用者の心理的な抵抗感に配慮した施設運営の一環であり、全国的に広く見られる傾向です。
どうしても友引の日にお葬式を行わなければならない場合には、「友引人形」と呼ばれる小さな人形を棺に入れる風習が用いられることがあります。この人形は、故人が友人を連れて行かないようにする「身代わり」としての意味を持ち、迷信的ながらも心の安寧を得るための手段として受け入れられています。
お葬式が「ダメな日」大安や仏滅は避けるべき?
六曜の中でも「大安」と「仏滅」は、対照的な意味を持つ日柄として知られています。大安は「大いに安し」とされ、物事が穏やかに進む吉日とされており、結婚式や地鎮祭などの慶事に選ばれることが多いです。そのため、弔事であるお葬式を大安に行うことに抵抗を感じる人もいます。縁起の良い日に悲しみの儀式を行うことに違和感を覚えるという心理的な背景があるためです。
一方、仏滅は「仏も滅するほどの凶日」とされ、六曜の中でも最も縁起が悪い日とされています。一般的には慶事を避ける日とされますが、お葬式に関しては必ずしも不適切とは限りません。むしろ、仏滅は「悪縁を断ち切る日」として再出発に適していると考える人もおり、故人を送る儀式にはふさわしいとする見方もあります。
重要なのは、六曜が仏教とは無関係であるという点です。仏教の教義には六曜に関する記述はなく、宗教的な制約は存在しません。浄土真宗などの宗派では、六曜を気にすること自体を否定する立場を取っている場合もあります。
したがって、お葬式の日取りを決める際には、六曜の意味を過度に気にする必要はありません。ただし、参列者の中には六曜を重視する方もいるため、風習や地域性、個々の価値観に配慮した判断が求められます。
お葬式が「ダメな日」の「日取りカレンダー」とは?
お葬式の日取りを決める際には、お葬式が「ダメな日」の「日取りカレンダー」として、六曜が記載されたカレンダーを参考にすることが一般的です。上でも説明したとおり、六曜は仏教と無関係であるため、お葬式の日取りを決める際に、六曜を過度に気にする必要はないのですが、現実的には、参列者をはじめ六曜を気にする傾向は存在するため、六曜が記載されたカレンダーを参考にお葬式の日取りを決める配慮が推奨されます。六曜には以下の6種類があり、それぞれに吉凶の意味があります。
| 六曜 | 読み方 | 意味・特徴 |
| 先勝 | せんしょう | 午前中が吉、午後が凶。急ぐほど良いとされる |
| 友引 | ともびき | 朝晩が吉、正午前後が凶。弔事には不向きとされる |
| 先負 | せんぶ | 午前が凶、午後が吉。静かに過ごすのが良いとされる |
| 仏滅 | ぶつめつ | 一日を通して凶。慶事には不向きだが弔事には問題なし |
| 大安 | たいあん | 一日を通して吉。慶事に最適とされる |
| 赤口 | しゃっこう | 正午前後のみ吉。それ以外は凶とされる |
このように、六曜には時間帯による吉凶も含まれており、単に日付だけでなく時間にも注意が必要です。特に友引や仏滅は、お葬式の日取りとして避けられることが多いため、カレンダーで確認することが重要です。
ただし、六曜は占いの一種であり、科学的根拠や宗教的な裏付けはありません。あくまで参考程度にとどめ、火葬場の空き状況、僧侶の都合、参列者の予定など、実務的な要素を優先して日程を決定することが現実的です。
お通夜が「ダメな日」とされる日柄とは?
お通夜は、故人を偲び、霊を守るために行われる儀式であり、お葬式とは異なる意味を持ちます。お通夜は一般的に、故人が亡くなった翌日に行われることが多く、夜間に執り行われるのが通例です。
上でも説明した通り、六曜の中でも「友引」はお葬式の日取りとして避けられる傾向がありますが、お通夜に関しては必ずしも問題視されるわけではありません。お通夜は故人との別れの準備段階であり、正式な告別式ではないため、一般的には友引の日に行っても支障はないとされています。
とはいえ、友引や仏滅などの六曜を気にする方も一定数存在するため、日柄に配慮することが望ましいかもしれません。特に地域の風習や参列者の考え方によっては、お通夜の日取りにも慎重な判断が求められる場合があるからです。
実際にお通夜の日程を決める際には、僧侶の都合や火葬場の予約状況を確認することが不可欠です。僧侶のスケジュールが合わない場合は、菩提寺に早めに連絡を取り、調整を依頼することが推奨されます。また、火葬場の空き状況によっては、通夜と葬儀の日程をずらす必要が生じることもあります。
柔軟な対応と丁寧な調整を行うことで、参列者にとっても心地よい儀式となり、故人を穏やかに送り出すことができます。
まとめ:おお葬式を「避けるべき日」「ダメな日」は本当にあるのか?
本記事の内容をまとめると次のとおりです。
- 六曜は仏教とは無関係であり、葬儀の日取りで気にしすぎなくてよい
- 友引は「友を引く」とされお葬式には避けられる傾向がある
- 火葬場が友引に休業する地域もある
- 大安は慶事向きで葬儀には不向きとされることもある
- 仏滅は縁起が悪いが葬儀には問題ないとされる
- 赤口は時間帯によって吉凶が分かれる
- 葬儀の日程は死後24時間以降で調整する必要がある
- 事故死では検死などで日程が延びることがある
- お通夜は翌日または当日に行う地域もある
- 保冷措置によりお葬式の日程調整が可能になる
- 前火葬で柔軟なスケジュールが組める場合もある
- 参列者の都合もお葬式の日程決定の重要な要素である
- 地域の風習を尊重することが円滑なお葬式につながる
- 僧侶や葬儀場の空き状況を早めに確認すること
- 家族で話し合い納得できる葬儀日程を選ぶことが大切

